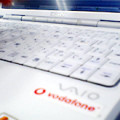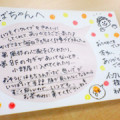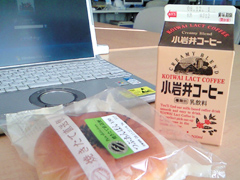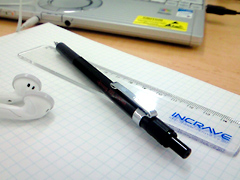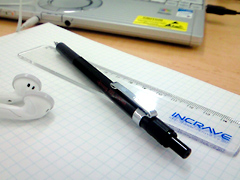会社に入りたてのころは会議に参加させてもらっても、書記係です(笑)。
ホワイトボード前に立たされて 「しっかりとまとめていってね」 と初めて言われたときは、気を失いそうになりましたが、とにかく挑戦。 「ずいぶん字が汚いなぁ」 は予想どおり(^^;。 一番びっくりしたのが 「真ん中から書き始めなさい」 と言われたことでした。
左上から書いていくのが常識でしょ。 「なんで真ん中なんだろう」 という顔をしていると、「書き始めたことがいつも思考のスタートだと思うな」 と。 実際に、真ん中に書いたことから 「下」 や 「右」 に展開していくことは当然でしたが、「上」 や 「左」 にも考え方が伸びていき、想像もしていなかったような判断レベルが現れていく。 マジックを見ているみたいな衝撃。
以来、この思考開発法を身につけてきました。 先輩たちの チャンスメイク にも感謝。 何でも 「真ん中から考えはじめる」 と、いいです。